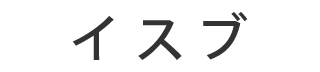精神障害者保健福祉手帳について詳しくご存知ですか?
手帳を取得する事で様々なサービスが受けられますので、取得できれば今の生活を少しでも改善する事が出来ると思います。
そこで今回は、精神障害者保健福祉手帳を所持するメリットとデメリットについてまとめました。
手帳の申請を検討されている方は是非目を通してみてください。
精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
精神障害者保健福祉手帳を所持するメリットとは?

障害福祉サービス
訪問系サービス:在宅等で訪問を受けたり、外出時の支援等をするサービス。
日中活動系サービス:施設などで昼間の活動を支援するサービス。
居宅系サービス:入所施設などで住まいの場としての支援をするサービス。
障害児通所サービス:18歳未満の障害児が施設に通所し、障害に応じた指導や訓練を受けられます。
自立支援医療
障害を軽減する治療等を、指定自立支援医療機関で受ける場合の公費負担制度。
精神疾患のために通院し、健康保険証を使って病院や診療所などでかかった医療費の一部が支給されます。(精神通院医療)
費用の1割が自己負担となります。(所得に応じた自己負担上限額あり)
障害者雇用
国や地方公共団体、事業主に対して、一定率以上の障害者を雇用する義務が法律で課せられています。
身体障害者手帳を持っていると就職を目指すとき、一般採用だけでなくこういった障害者雇用での募集にも応募できるので有利です。
運転免許取得費の助成
障害者が、就労等のために普通免許を取得した場合、免許取得に要した費用について助成金を交付。(助成額は地域により異なります)
税金の控除、非課税
所得税の控除
1級:40万円 / 2・3級:27万円
贈与税の非課税
1級:6,000万円まで非課税 / 2・3級:3,000万円まで非課税
相続税の控除
1級:85歳に達するまでの年数1年につき×20万円 / 2・3級:85歳に達するまでの年数1年×10万円
参考:国税庁 障害者と税
自動車税、自動車取得税の減免
都道府県によって違いがありますが、東京都では1級のみが減免の対象になります。
参考:東京都主税局 自動車税・自動車取得税の減免制度のご案内
NHK放送受信料の免除
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が世帯主で受信契約者の場合、50%割引。
受けられるサービスについてはこちらの記事にさらに詳しく解説しているのであわせてご覧ください。▼
その他の様々なメリット
交通機関の割引
- 飛行機チケットの割引
- バス運賃の割引
- タクシー利用券の交付
- 船、フェリーの割引
※JR運賃、有料道路の割引は残念ながらありません。
携帯電話料金の割引
各社それぞれ名称が異なりますが、障害者手帳を所持していると割引を受ける事が出来ます。
基本料金の他にも様々な割引を受けることが出来ますので、詳しくはそれぞれのサイトで確認してください。
その他、商業施設の障害者割引
- 映画館チケットの割引
- 水族館入館料の割引
- 東京スカイツリー入場券の割引
- ユニバーサルスタジオジャパンのスタジオパスが割引
など
障害者割引についてもう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。▼
精神障害者保健福祉手帳を所持するデメリットとは?

障害者手帳を所持するデメリットは、重度の障害者の場合特にありません。
軽度の障害をお持ちの方で、障害を人に知られたくない人にはそのリスクがある為、デメリットに当たるかもしれません。
就職や会社での扱いについて
障害者手帳を所持することのデメリットとして気になることが、就職が不利にならないかということだと思います。
基本的に、障害者手帳を所持していることは会社に報告する義務はありませんので、個人の判断において、開示せずに一般採用で就職活動をすることは可能です。
ただし、就職してから、所得税の障害者控除を受けたい場合などは、会社に書類を提出する必要があるため、障害者であることが明らかになります。
もし、障害者であることを明かしたくない場合は書類の提出をせずに、自分で申告を済ませなければいけないなどの手間がかかる可能性があります。
手帳の更新もお忘れなく
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間で、有効期間の延長を希望する方は更新の手続きを行うことになっています。
更新しない場合は申請の必要はありません。
更新時期
手帳の更新は有効期限の日の3か月前から行うことができます。
期限切れの場合でもその後、更新申請を行う事が出来ます。
更新手続きの方法
更新手続きには最初の申請時と同様に、主治医の診断書または年金証書等の写しが必要です。
更新申請書を添えて、担当窓口で申請を行ってください。
更新忘れの無いように、忘れずに手続きを行ってください。
更新手続きについては合わせてこちらの記事もご覧ください。▼